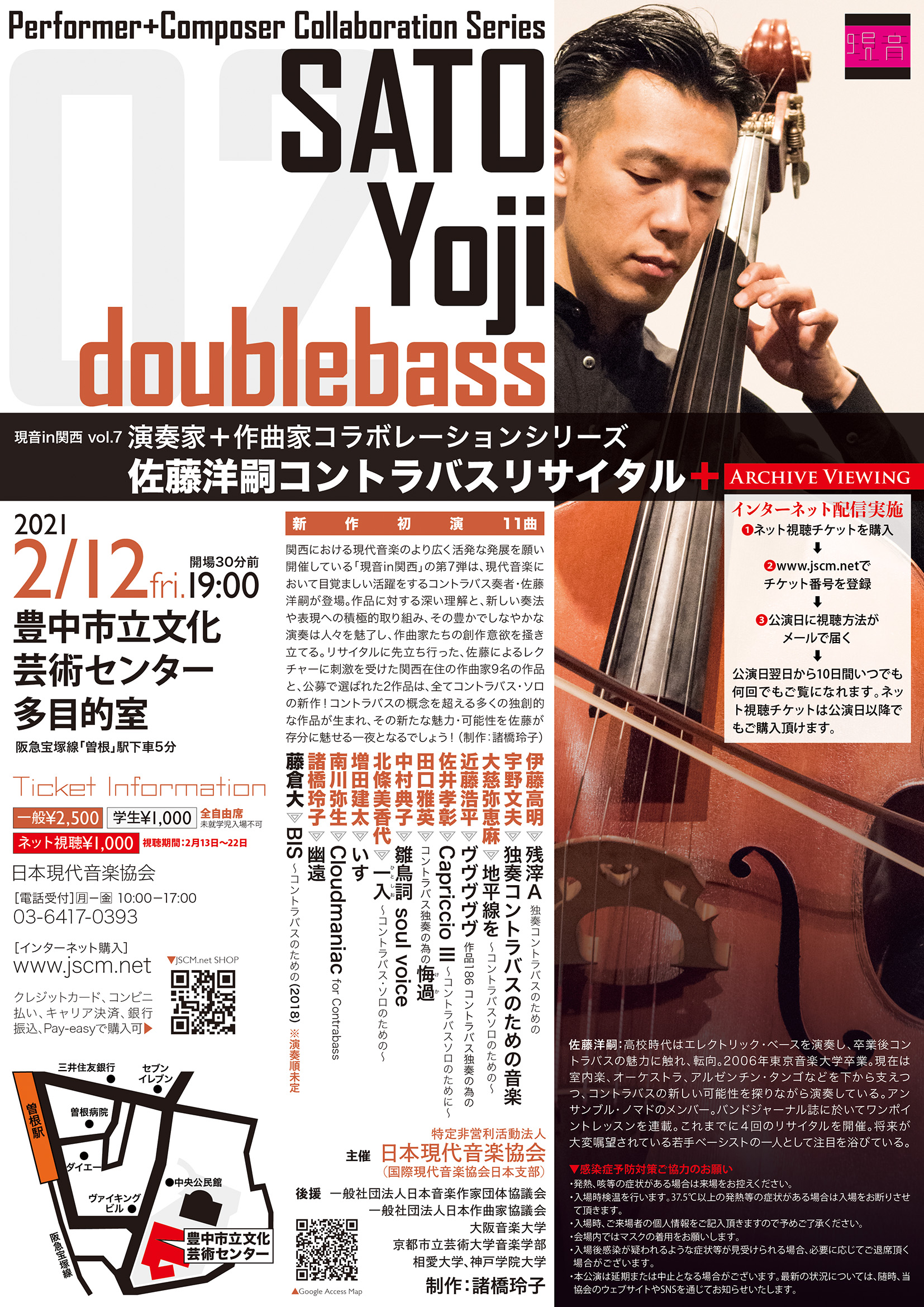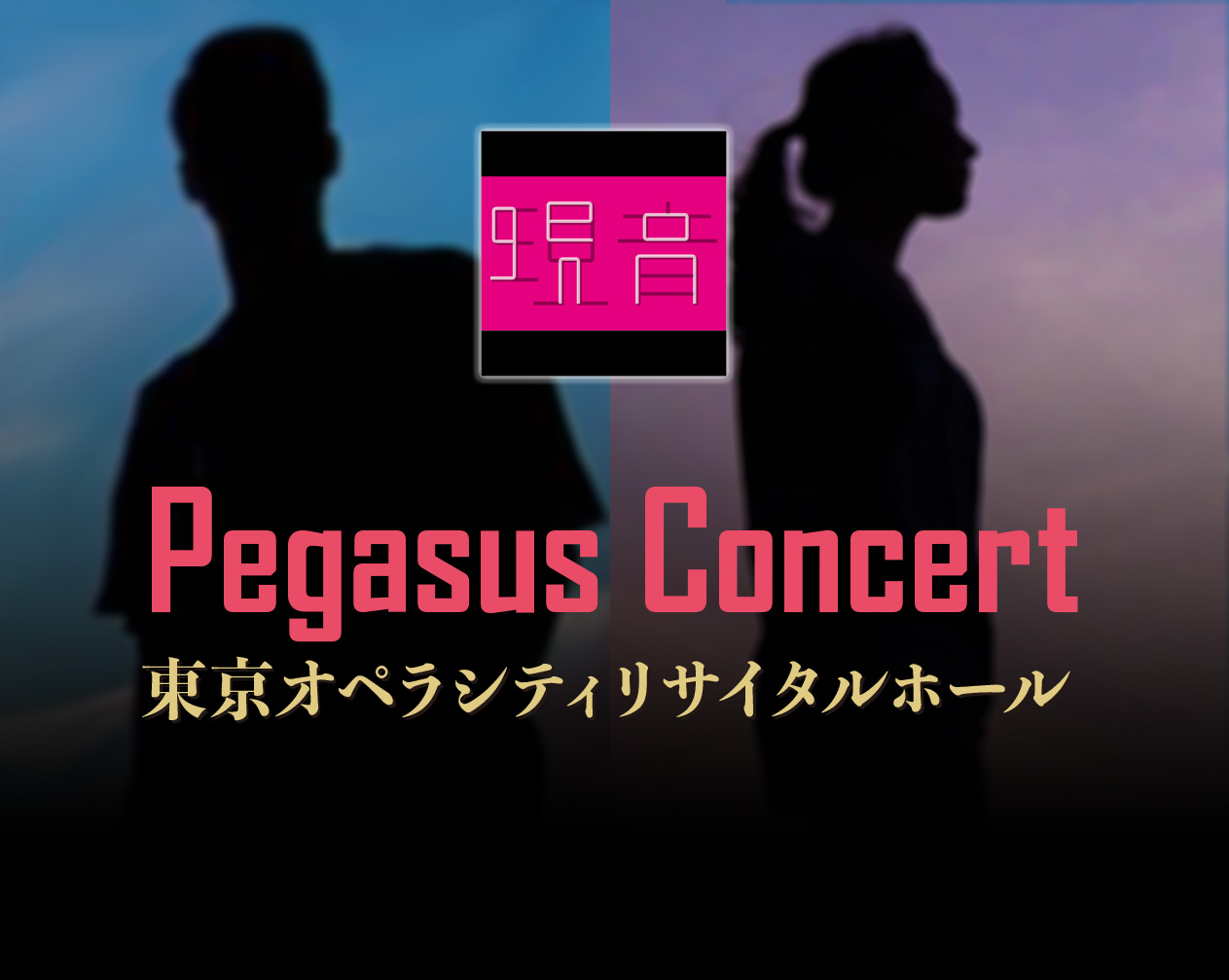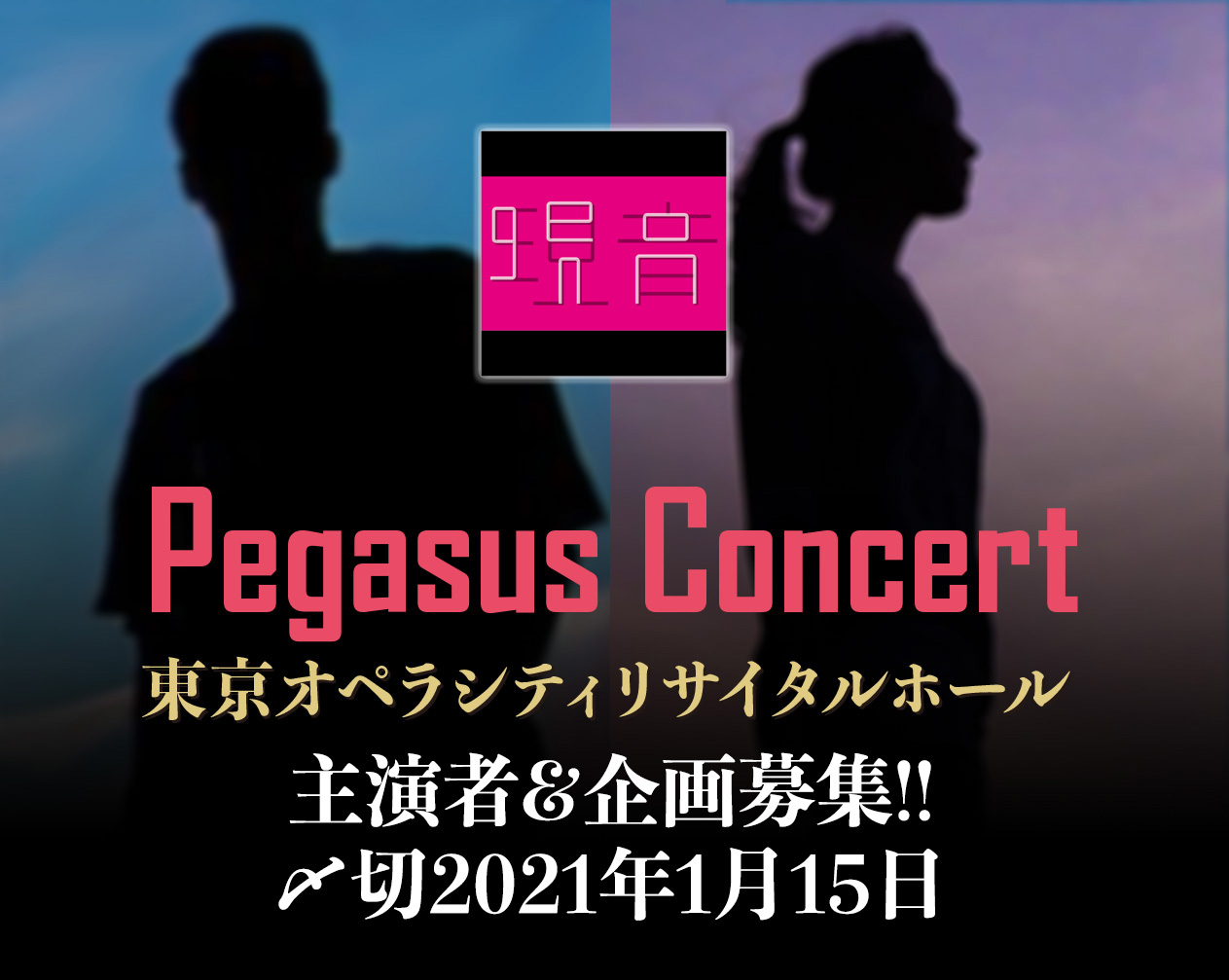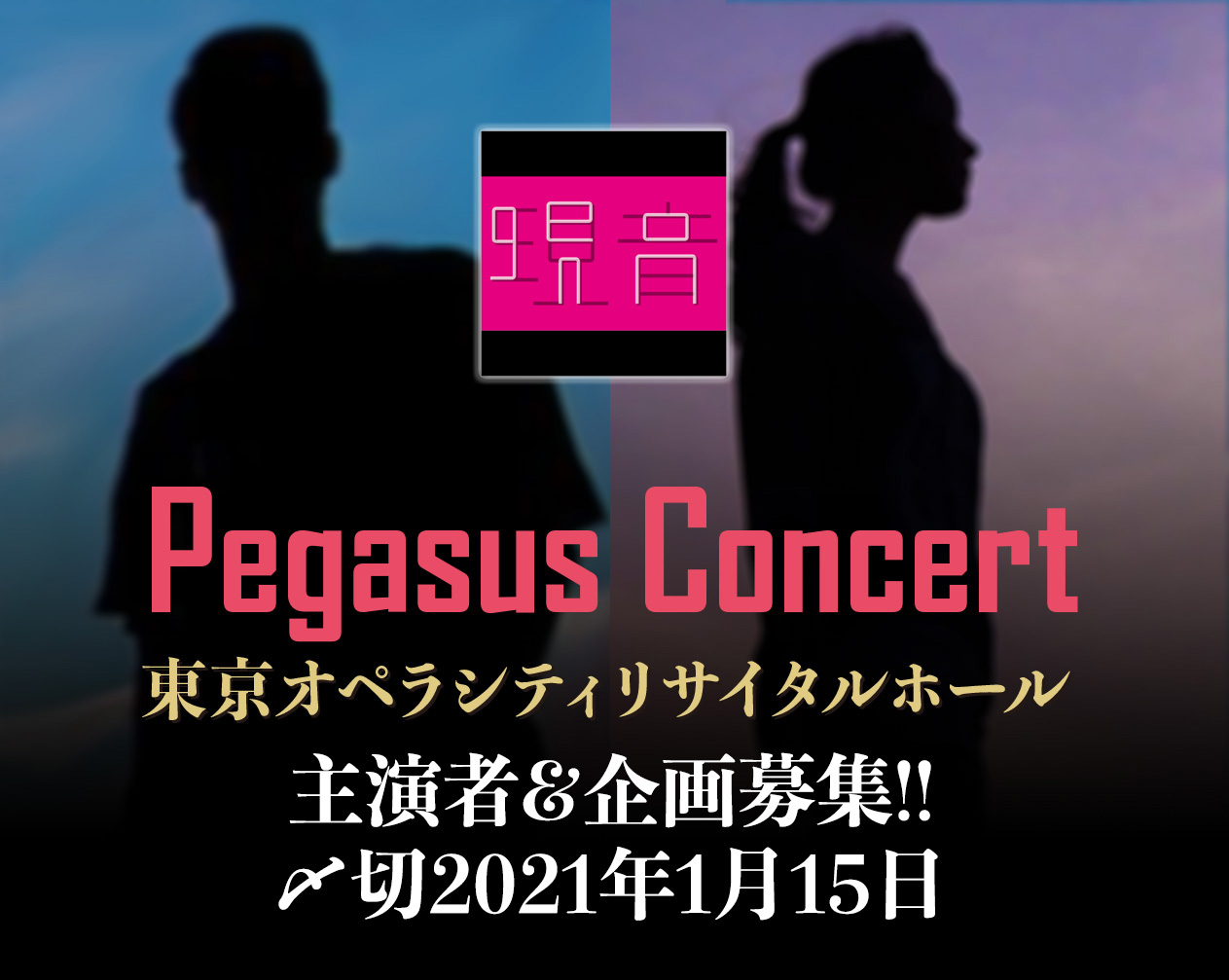
〈現音 Music of Our Time 2021〉
「ペガサス・コンサー トVol.III」募集要項
主催:日本現代音楽協会
「ペガサス・コンサート」は、現代音楽作品の演奏に意欲的な演奏家を支援するシリーズです。演奏家が自ら企画立案して出演するリサイタル企画を広く募集します。応募者の年齢、国籍は問いません。個人、団体のいずれの応募も可能です。また、演奏分野、演奏楽器に制約はありません(電子楽器、エレクトロニクスの使用も可)。なお、応募は無料です。
●開催日時・会場
「ペガサス・コンサート」は、2021年11月から12月にかけて開催される当協会の音楽祭〈現音 Music of Our Time 2021〉の中で、下記の日程で行われます。公演のインターネット配信も行う予定です。
第1回公演:2021年12月6日(月)19:00開演(18:30開場)21:00終演
東京オペラシティ リサイタルホール
第2回公演:2021年12月7日(火)19:00開演(18:30開場)21:00終演
東京オペラシティ リサイタルホール
★上記のどちらの日程でも出演可能なことが応募の条件となります。
●会場費
上記二公演とも、演奏会当日の午後・夜間枠の会場費を協会が負担します。
●制作費補助
上記二公演とも、演奏会制作費補助として、協会より50,000円を提供します。
●チラシとプログラム冊子の制作
〈現音 Music of Our Time 2021〉の共通チラシ、ならびに共通プログラム冊子を協会が用意し、かつ制作費と印刷費を負担します。
●その他の経費
著作権料と会場付帯設備費は出演者が負担して下さい。また楽器借用料(ピアノを含む)、楽器調律料、楽器運搬費も出演者の負担となり、それらに必要な諸手配は出演者が行って下さい。
●プログラムの条件
(1) 原則として、1945年以降に作曲された作品で、2時間内の演奏会(休憩、転換を含む)を企画・構成して下さい。ただし企画の趣旨に沿うものであれば、1945年以前に書かれた作品を若干含む事も可とします。
(2) 初演の作品を1曲以上含めて下さい。(海外で初演された曲の)日本初演も可とします。なお、新作を作曲家に委嘱する場合は、出演者が用意するものとします。
(3) プログラムの曲目の少なくとも3分の1以上を日本人作品とします(できれば2分の1以上が望ましい)。
●チケットの券売と収入について
入場料は座席券が3,000円、インターネット視聴券が1,500円です。出演者へのチケットノルマはありませんが、極力、券売・集客にご協力下さい。なお、リサイタルで得られたチケット収入は、出演者がその3分の1、協会がその3分の2を収めるものとし、別途に出演料は発生しません。
●応募手続き
2020年12月16日(水)〜2021年1月15日(金)18:00必着。郵送または宅配便による送付のみとします。以下の書類(書式自由)と資料をまとめたものをお送り下さい。
1 . a: 応募者氏名、もしくは応募団体名とその代表者氏名 b: 応募者(応募団体代表者)の住所、電話番号、Eメールアドレス
2. 応募者(応募団体)の演奏活動実績を中心としたプロフィール
3. 応募者(応募団体)による近年の演奏の録画データ2曲以上
※1945年以降に作曲された作品の演奏としますが、リサイタルで演奏を予定している作品以外でも構いません。なお、録画データの提出が困難な場合のみ、録音データでも可とします。録画、録音は、パソコンで再生可能なデータをUSBメモリ等のメディアに収めたもの、またはDVD/Blu-ray/CDプレーヤーで再生可能な光学ディスクを提出してください。YouTubeなどのインターネットサイトへのリンクを提出資料とする事、データ便による提出は不可とします。応募資料の返却は致しません。
4. リサイタルのサブタイトルと、企画・構成の趣旨を説明したもの
5. リサイタルの全演目と各曲の演奏時間
※未定は一切不可とします。
●結果発表
募集締め切り後、協会理事会にて審査を行い、2021年1月末日までに二企画の採用を決定し、協会ウェブサイトで公表します。
●応募先・問合わせ先
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-19-6-2F
日本現代音楽協会(国際現代音楽協会日本支部)
TEL: 03-6417-0393(平日10:00-17:00)
E-mail: 80th@jscm.net
 日本現代音楽協会が関西における現代音楽の活発な発展を狙い開催している「現音in関西」の第8弾。オーケストラの奏者として、またソロでは現代音楽の分野でも活動している矢巻正輝氏を迎え、来年開催される、全作初演のリサイタルに先立ち、トロンボーンの奏法などについて実演を交えレクチャーを行う。日本現代音楽協会の会員のみならず、一般の作曲家やトロンボーン専攻生、管楽器専攻生、作曲専攻学生も聴講可能。 コンサートでは、会員の作品の他、一般、学生からも広く作品を公募し、トロンボーン・ソロの作品を選出し初演する。(コンサート日時未定)
日本現代音楽協会が関西における現代音楽の活発な発展を狙い開催している「現音in関西」の第8弾。オーケストラの奏者として、またソロでは現代音楽の分野でも活動している矢巻正輝氏を迎え、来年開催される、全作初演のリサイタルに先立ち、トロンボーンの奏法などについて実演を交えレクチャーを行う。日本現代音楽協会の会員のみならず、一般の作曲家やトロンボーン専攻生、管楽器専攻生、作曲専攻学生も聴講可能。 コンサートでは、会員の作品の他、一般、学生からも広く作品を公募し、トロンボーン・ソロの作品を選出し初演する。(コンサート日時未定)