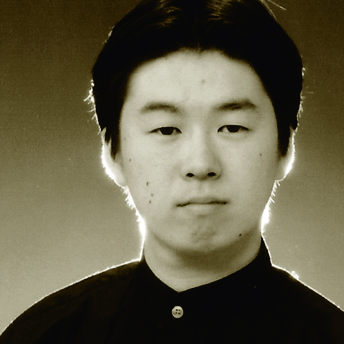現代の音楽展2015 第2夜 西川竜太の啓く<現代合唱の世界>〜第21回朝日現代音楽賞受賞記念演奏会〜 開催を終えて
松尾 祐孝
日本現代音楽協会は、1930年に新興作曲家連盟して産声を上げて以来、80有余年の歴史を紡いできました。その節目には、創立60周年記念として〈東京現代音楽祭〉(1991年)、70周年記念として〈ISCM世界音楽の日々2001横浜大会〉(2001年10月)等を開催してきました。そのような流れの中で、80周年記念として開催した〈現音・特別音楽展2011「新しい音楽のカタチ」〜軌跡と未来〜2daysコンサート〉(2012年1月)全5公演の中の1公演は、西川竜太氏指揮によるヴォクスマーナの演奏に託され、様々なスタイルの作品がそれぞれに彫琢された充実した内容が具現して、大きな反響が上がりました。
1996年に創設されたヴォクスマーナとの長年にわたる協働・協創に象徴される大活躍によって、西川竜太氏は日本の現代音楽シーンに確固たる地歩を築いてこられました。加えて、数多くのアマチュアや大学等の合唱団やアンサンブルの指導・育成からも、最先端の現代作品の初演や再演を数多く生み出してこられました。そういった活動が高く評価されて、西川氏が2011年度「第21回朝日現代音楽賞」を受賞されたことは、作曲家である私どもとしても大いなる歓びとなりました。そして、このような経緯を経て、西川氏を主人公とした“第21回朝日現代音楽賞受賞記念演奏会”を開催することになりました。
演奏は、ヴォクスマーナ、女性合唱団 暁、混声合唱団 空、男性合唱団クール・ゼフィール、成蹊大学混声合唱団の5団体にお願いすることになりました。西川氏からの、共に歩んでこられたお仲間、そして手塩にかけて育ててこられた合唱団が一堂に会する企画にしたいという強い想いが、このようなカタチになりました。プログラムは、西川氏の推薦による会員作曲家への新作出品の依頼と出品作品の公募枠を組み合わせて策定されていきました。さらに、企画策定中に公演当日が当協会会長の福士則夫氏の70歳の誕生日ということに気付きました。その結果、皆様ご存知の通りの6作品による演奏会が実現する運びになりました。
横島浩作品《Belle de jour 昼顔》から今夜のただならない内容の充実の予感が始まり、神長貞行作品《DEGITAL BOX 2》では、正岡子規一派と与謝野蕪村の俳句を柔軟にトレースしながら様々な発音が飛び交い、福士則夫作品《霧とカムイ》では、演奏者が聴衆を囲むように配された中心で西川氏がタクトを執り、照明がおとされた空間と歌唱が織り成す時空が心に滲みる時間となりました。山本裕之作品《失われたテキストをⅠ求めて》では、言葉と音楽の関係性の再構築に挑む可能性が意欲的に提示され、松平頼曉作品《A person has let the“Kelly”out of the bottle》では、人間の様々な感情を描いた音楽が氏独特の数字マジックによるオーダーで配された松平ワールドが現出、最後の湯浅譲二作品《混声のためのプロジェクション》では、歌唱による音響が空間を見事に彩っていった。
6曲6様、6作曲家6様の個性の発露と演奏の充実によって、聴衆の皆さんの反応はとても好意的でした。また作曲家と演奏家の双方の達成感も高い様子が伺えました。終演後、客出しを終えたロビーに出演合唱団のメンバーが西川氏を囲むように集まってきて、終いには作曲家も交えて大人数の記念撮影まで始まりました。演奏会の充実と、西川氏と共に歩んでこられた方々の固い絆を強く感じた、心温まる一コマでした。
最後に、企画策定段階から絶大なるご協力とともに公演に向けて各作品を見事に彫琢していただいた西川竜太氏、素晴らしい演奏を披露していただいた各合唱団の皆様、共催としてご協力いただいた朝日新聞社の関係者の皆様、その他、助成やご支援をいただいた皆様に、厚く御礼申し上げます。
「現代合唱」はその範疇を超えて
山本 裕之
2月15日は合唱指揮者である西川竜太氏の、第21回朝日現代音楽賞受賞記念演奏会が行われた。題して「西川竜太が啓く現代合唱の世界」。しかし実は、彼の演奏活動を「合唱」というカテゴリーで語るのは難しい。どちらかというとそのフィールドは、ヴォーカル・アンサンブルという土壌で考えた方がしっくりくるだろう。
西川氏については、20年近く続くヴォクスマーナ(Vox humana、1996~)を率いた活動がよく知られている。「人間の声」という名前のこのグループは、近年は約12人前後で活動しているので、いわゆる合唱というには規模が小さい。また当初はルネサンス音楽をプログラムに入れていたが、近年は専ら日本人作曲家の委嘱作を中心に演奏している。そして彼は作曲家に「何を書いても良い」との依頼の仕方をするので、作曲家もこの先鋭的なアンサンブルを知っている上で、合唱というよりは「個」の集まりとしてのヴォーカル・アンサンブルという意識で曲を書くことが多い。したがって、西川氏は自らが多大な影響を受けた合唱指揮者の田中信昭氏を尊敬するも、形態の異なるヴォーカル・アンサンブル寄りの開拓を続けた結果、日本のこれまでの声楽作品の世界では手薄だったこの分野に大きな風穴を開けたのだ。彼が朝日現代音楽賞を受賞したのも、この点が大きく評価されたのだろうと思われる。
もちろん、単に長く活動を続けてきただけではなく、この日の公演を聴いた人ならばきっと、そのクオリティの高さを感じたに違いない。日頃からいかに西川氏が、ピッチやリズムといった西洋音楽における中心的な技術を、現代声楽で器楽同様あるいは器楽を超えてシビアに正確に実現するかを大切にしてきたか。その結果立ち現れる声楽「アンサンブル」の魅力が、西川氏の集大成として顕れたのがこの日の公演だった。ヴォクスマーナ、男声合唱団クール・ゼフィール(1993~)、女声合唱団「暁」(2007~)、混声合唱団「空」[くう](同)に加えて、いわゆる「合唱」の規模と形態を取る成蹊大学混声合唱団(2007より常任指揮)によって現音会員の6作品がこの日演奏された。
会員公募作品は横島浩氏の《Belle de jour 昼顔、初演》(2013)。ケッセルの小説『昼顔』の中から性描写部分と数年前に国内に出回った「謎の怪文書」を早口でまくし立て、それと被さるように不貞の色が漂うジェズアルドのマドリガルが、女性合唱団「暁」によって美しく響き渡る。どれも言葉はほぼ聴き取れないため、響きが飽和した状態が始終続くが、むしろ音響の構成体としての側面が強調される。
2曲目はこの日最も人数の多い成蹊大学混声合唱団による神長貞行氏の《DIGITAL BOX 2》(2014)。このシリーズで作曲者は「言葉や、言葉と言葉の連なりを全て『DIGITALな点の集合体』とみなしている」という。しかし曲の冒頭から口による様々なノイズが現れ、その関心は言葉の問題だけに留まらない。一方でユニゾンがこの日最も際立ったのがこの作品だった。合唱の古典的かつ永久の響きとしての「声のユニゾン」が非常に効果的に使われていた。
前半最後は福士則夫氏の《霧とカムイ》(2014、初演)。伊賀ふで詩集『アイヌ・母の歌』に大きな衝撃を受け、その世界をヴォクスマーナの演奏に乗せた。この作品で作曲者は、12名の演奏者を会場の観客を取り囲むように配置し、指揮者を真ん中に配置した。「合唱」は解体され個々の声が会場内で呼び交わし合い、ぐるぐる回り、グループを組み、響きのみならず構造も効果的に立体化した。叙情的内容のテキストを、西川+ヴォクスマーナはただの「歌」に終わらせなかった。
休憩を挟んで演奏された拙作の《失われたテキストを求め I》(2009/13)はこの日最も古い作品。改訂前を含めてこの日が三度目の演奏になる。演奏者によって選ばれたテキストが事前に作曲されている楽譜に機械的にはめ込まれるため、言葉は不確定的に聞き取りにくくなる。会場の響きも考慮しながら8名のクール・ゼフィールは、ルネサンス以降の「音楽に付されたテキストの聞こえにくさ」という問題を、絶妙なバランスで実現していた。
松平頼曉氏《A person has let the “Kelly” out of the bottle》(2013-14、初演)はこの日二回目の出演である「暁」が、横島作品とは全く異なるスタイルの作品に挑戦。自動翻訳機で日本語と英語を行き来させ意味が通らなくなったテキスト(松井茂の詩)に、インド古典芸術で重要視される九つの感情、すなわちヒロイズム、エロティシズム、驚き、落ち着き、悲しみ、憎悪、怒り、恐れ、歓喜を明確なブロック構造にはめ込んだ。仕組みの誤用を音楽構造枠に当てはめ、人間的な感情をメタレベルで表現するという、何重にも筋違いなレイヤーを重ねた松平氏ならではの音楽を「暁」は見事に演奏した。
西川氏は松平頼曉氏の「個展」を過去に二度開催している一方で、湯浅譲二氏の個展も二度(主催ではないものも含めれば四回)行っており、この両作曲家の作品に対する意欲は並のものではない。この日最後の湯浅作品《混成のためのプロジェクション》(2015、初演)は、過去から連なる氏の実験的な合唱作品の一つの到達点であり、母音によるエネルギーの推移が人間の声という生々しい媒体で駆け巡る、湯浅氏の音楽語法が見事に現れたものであった。20名からなる混声合唱団「空」が演奏したこの作品で、西川氏の得意とする声楽アンサンブルは同時に、合唱としての表現も再獲得し、この日の充実したコンサートの幕を閉じた。